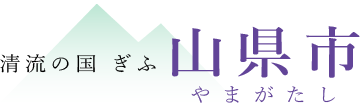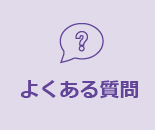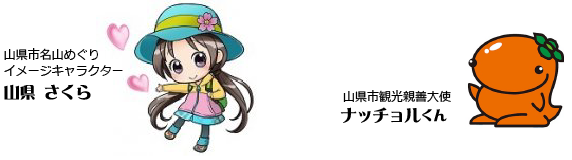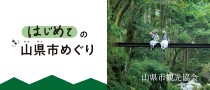本文
山県市妊婦のための支援給付事業
山県市妊婦のための支援給付事業について(令和7年4月1日開始)
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、こども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支援給付の対象
1回目妊娠時(5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けた人
※産科医療機関などを受診し、胎児の心拍を確認した妊婦に限ります。金銭的な理由で妊娠判定のための受診ができない人は、子育て支援課へ相談してください。 妊娠判定受診費用の助成
2回目出産後(こども1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出を出した人
申請方法
妊娠の届出時に申請者(妊婦)が専門職(保健師・助産師など)との面談を実施し「妊婦給付認定申請」をします。また、出産後の赤ちゃん訪問時に「胎児の数の届出」を申請します。
妊娠中や産後の体調などの理由で、専門職(保健師・助産師等)との面談や申請が難しい場合は、子育て支援課に相談してください。
申請期限
- 1回目 胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日から2年
- 2回目 出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日に死産または流産したときはその日)から2年
※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた人、出産後にお子さんが亡くなられた人も対象です。
給付方法
妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦以外の口座名義には指定できません。
流産・死産などを経験された人へ
令和7年4月1日以降、妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された人は妊婦支援給付金の給付対象となります。
※妊娠届出前に流産・人工中絶などを経験された人も胎児心音が確認されていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要です。(任意様式)
給付を申請する場合は、子育て支援課(0581-22-6839)に問い合わせてください。
申請方法
専用フォーム(作成中)か子育て支援課窓口で申請してください。
申請に必要な持ち物
母子健康手帳(14ページの医師による記載)
※母子健康手帳を持っていない場合は、医師による妊娠・流産の事実が分かる診断書・マイナンバーカード
リーフレット
「妊婦のための支援給付」のご案内 [PDFファイル/767KB]
流産・死産された人の給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/258KB]