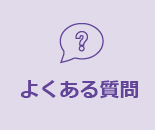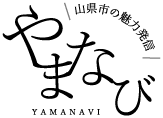本文
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月分の手当から、所得制限の撤廃、高校生年代(18歳になってから最初の3月31日まで)までの支給期間の延長など、制度が改正(拡充)されます。
詳しい内容は、
「改正(拡充)のお知らせ」 [PDFファイル/343KB]をご覧ください。
児童の属する世帯に案内を送付(8月上旬予定)します。改正により新たに受給資格が生じる人は、申請が必要になりますので手続きをしてください。世帯主が祖父母などの場合で案内が届いたときは、支給の対象となる者に確認してください。
(注)子と別居している場合や、市に申請履歴が無い場合等、案内を送付できない場合があります。案内通知が届かない場合でも「児童手当拡充 申請の必要・不要 確認フローチャート」で確認いただき、新たに受給資格が生じる人は、申請が必要になります。
対象者
- 高校生年代の児童の保護者の人
・中学生以下の児童を養育していない人
・児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している人 - 所得上限限度額超過による受給事由の消滅か却下の通知を受けている人
※申請が必要か不要かの確認については、
「児童手当拡充 申請の必要・不要 確認フローチャート」 [PDFファイル/99KB]をご覧ください。
申請書
申請書は下記から様式をダウンロードできます。
※郵送での提出される場合は、「必要な添付書類」の写しを必ず添付してください。
| 手続きが必要な方 | 手続方法・必要な書類 |
|---|---|
|
(1) 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人 |
【必要な添付書類】
|
| (3) 児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育している人 |
【必要な添付書類】
|
提出方法・提出先
郵送の場合
〒501-2192 山県市高木1000番地1
山県市役所 子育て支援課 児童手当担当宛
※郵送申請の場合はコピー(個人番号記載の住民票を添付する場合は原本)を同封してください。
電子の場合
| 認定請求となる人<外部リンク> | 額改定請求となる人<外部リンク> |
|---|---|
 |
 |
窓口の場合
山県市役所 保健福祉ふれあいセンター1階 子育て支援課 児童手当担当
※各支所では受け付けしていません。
申請期限
令和6年9月30日(金曜日)
申請書(添付書類を含む。)は、9月30日までに提出してください。
認定となる人で、9月30日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼっての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を市で受け付けした月の翌月分からになります)。9月30日以前に市から転出する場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
経済的な負担などがある18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる人
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。18歳年度末以降~22歳年度末(以下「大学生年代」という。)までの子で、児童手当受給者(申請者)がこどもの生計費などを経済的に負担していて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、上の子としてカウント対象に含むことができます。
・同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している場合
・別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている場合
・就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合
・海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合
多子加算(対象児童と大学生年代の子を含めて3人以上)のカウント対象となる該当の子がいる場合は、次の書類を提出してください。
- 認定請求書 [PDFファイル/139KB]または額改定認定請求書 [PDFファイル/122KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/56KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/118KB] - その他添付書類
a 対象となる子の個人番号確認書類の写し
b 学生の場合は、在学証明書(原本)や学生証の写し
c 対象となる子の健康保険証の写し など
公務員の人
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期などは、それぞれの勤務先(所属庁)へ問い合わせてください。